千曲万来余話その703「秋の夜長にショパン協奏曲1番を一枚いかが ? ・・・」
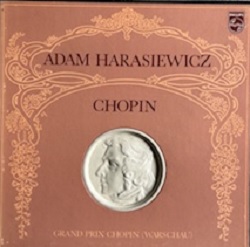 TVから今年の夏は3週間ほど長いとか、始め1週間早くお仕舞いは2週間遅くなっているそうだ。その分春と秋は短く冬は変わらずとか1年間を通すとその傾向が分析されたという。
TVから今年の夏は3週間ほど長いとか、始め1週間早くお仕舞いは2週間遅くなっているそうだ。その分春と秋は短く冬は変わらずとか1年間を通すとその傾向が分析されたという。
今の時期札幌の北海道大学イチョウ並木は、ちょいと見頃、この並木道を歩くと何か仕合わせの予感がするといわれている。幸福の黄色、その黄金色は思考回路に影響を与えられることと想像するに難くない。多分北大生は知っている、観光スポットとしてこの時期こそ一推しかもしれない。
俗説の一つ、ショパンの協奏曲1番を元にして、あの48年ほど前の「北の宿から」は作曲された! とか、作曲者から当然のごとくNOの証言を発表。有名な中田喜直作曲「雪の降るまちを」これこそ幻想曲ヘ短調作品49激似説広まるも、なかださんからは敢然と曲の成立とは無関係という証言を発表なされて現在に至っている。やれベートーヴェンの皇帝協奏曲を元に「上を向いて歩こう」が作曲されたのではないか?とか、黛敏郎さんがテレビ番組で解説するも似ているのは確かなのだけれど、、、とか言及されていたのは50年余り前のこと。他にも例えば雪の降るまちを(1951)は古くから山形県鶴岡市に歌碑は建立されていて、旭川市神楽の大雪クリスタルホールにも20年余り前に歌碑は建立されている。つまり二つ、雪の降る町を人々は楽しんでいる。
ショパンのピアノ協奏曲2番ヘ短調作品21は1829年に作曲されていてつまりはティーンエージャーの手による作品、ホ短調の1番作品11は1830年とされている。2番はポーランドからウィーンへ渡る告別演奏会で初演されていて、なぜこの相違が発生したものかというと1番20歳の作品の楽譜が先に出版されたことと言われている。
そこよりも評論家たちの管弦楽法に言及する説でオーケストレーションは必ずしも十全ではないとする評論が、盤友人にとっても気になる話である。かいつまんでいうと、ヴァイオリン古典配置においては、まったく不足するところは無いと断言してさしつかえないだろう。現在の評論家たち現代のVnダブルウイングを破壊した下手配置型弦楽部を前提としているからの感想であり、舞台両袖に展開されるヴァイオリンの音色こそ古典配置の肝、現代札幌でも展開しているオーケストラ演奏会の風景である。放送やレコーディングという際にスピーカーから左側にヴァイオリン、そして右側にチェロやコントラバスの低音旋律が聞えるスタイルから評論するのには無理が有ろう。ショパンの2番協奏曲こそVn両翼配置の音楽会にて評論されることを提案する。
アダム・ハラシェヴィチ1932年生まれは、1955年第5回ショパンコンクールにてプリマの栄光を勝ち取り、2位に甘んじたウラディーミル・アシュケナージ1937年生れ、技巧性は確かにアシュケナージこそ無敵であろうことを否定するものではないのだが、故田中希代子1932年~96年彼女はそのコンクール10位、聴衆賞受賞という23歳だったが彼女としては、ハラシェヴィチの音楽性こそグランプリにふさわしいという発信をされていた。
ハインリッヒ・ホルライザー指揮したウィーン交響楽団1958年頃のフィリップス録音でこれは貴重な一枚。ピアノの音色は香わしく、大きなホールの残響豊かなスケール感は飛び切りという音盤。すなわち楽器の鳴り方で、倍音の高い音域に向かうスタインウエイなどマウリツィオ・ポリーニは1960年クレツキ指揮したフィルハーモニア管弦楽団との音盤で楽しんでいるのだが、明らかにハラシェヴィチのグランドピアノは左手の打鍵こそ男性的で雄渾、立派な楽器の鳴りっぷりを披露している。第2楽章ロマンツェを楽しむ時に、その音色の違い再生はオーディオの醍醐味であり「ベーゼンドルファー」というピアノを認知し探るこそ趣味特上愉悦といえるだろう・・・共演ウィーン交響楽団というクレジットは有力な判断材料といえるから。
